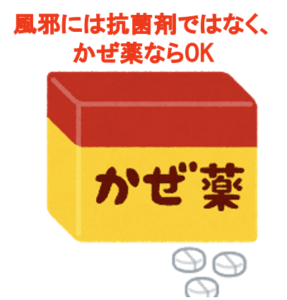皆さま、こんにちは。院長の梶谷です☺️
10月はノーベル賞受賞者の発表月ですね。
今年はなんと、ノーベル生理学・医学賞に坂口志文先生が、そして化学賞に北川進先生が選ばれました。
北川先生の業績である「多孔性素材」の開発については、院長はまったくの門外漢ですが、坂口先生の受賞理由となった「制御性T細胞(Treg)」の発見については、医学生時代に免疫学の先生が講義で触れていたのを思い出します。
もっと真剣に勉強しておけばよかった……と今さらながら思います😅。
さて今回は、「ノーベル賞と精神医学」についてお話ししたいと思います。
ノーベル賞と精神医学――この組み合わせで、院長の脳裏に真っ先に浮かぶ人物が一人おります。
それは、「ロボトミー手術」で悪名高いエガス・モニス博士です。
モニス博士はポルトガル出身の神経科医で、前頭葉と他の脳領域との神経連絡を切断する「ロボトミー手術」を開発しました。
当時、統合失調症は“不治の病”とされており、この手術は唯一の治療法として世界各地(日本を含む)で広く行われました。
手術を受けた統合失調症患者は「穏やかになる」とされ、当初は画期的な治療法として高く評価されたのです。この功績により、モニス博士は1949年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。
しかしその後、死亡例が相次ぎ、たとえ生存しても人格変化・感情の平板化・知的能力の低下といった深刻な副作用が多く報告されるようになります。次第に倫理的問題が強く指摘され、ロボトミー手術は「史上最悪のノーベル賞」と呼ばれるようになりました。
しかもモニス博士自身、65歳のときにロボトミー手術を受けた患者に銃撃され、身体に障害を負ってしまったといいます。
ノーベル賞という栄誉を手にしながら、のちに身体障害を抱える――まさに天国の時期と、良い時と比べて自身の活動が制限される事になるという、心が大きく揺れ動いた人生だったといえるでしょう。
この逸話は、私たちに多くのことを考えさせます。
当時は「画期的な精神科治療」として称賛された方法も、時が経てば厳しい批判の対象となる。
そんなことは、今後も起こり得るのではないでしょうか。
ノーベル賞級の輝かしい発見であっても、将来的には人類にとって有害なものへと変わる可能性は否定できません。
とりわけAI(人工知能)の発展は目覚ましく、いずれ人間の手に負えなくなる――映画『ターミネーター』に登場するAI「スカイネット」のような存在が現れるのでは……と、つい杞憂してしまいます。
そういえば、2024年はノーベル化学賞・物理学賞いずれもAI関連の研究が受賞していましたね。
科学技術の進歩はもちろん喜ばしいことですが、あまりに先へ進みすぎた技術が人間に牙をむかないことを願うばかりです。
 でのお問合せ
でのお問合せ でのお問合せ
でのお問合せ